
実は、資格を持っていなくても現場監督として仕事をすることは可能です。ただし、工事現場に配置が求められている「主任技術者」や「監理技術者」といった技術者として選任されるためには、「施工管理技士」の資格が必要になります。
「現場監督になるためには必ず資格が必要」というわけではありませんが、今後キャリアアップを目指していきたいと考えているのであれば、資格は取得しておいたほうが良いと言えるでしょう。
前述のとおり、「主任技術者」や「監理技術者」になるためには「施工管理技士」の資格が必要になります。この資格には7つの種類があります。また、それぞれの資格は「1級」と「2級」に分かれています。各資格の種類について紹介していきます。
施工管理技士の資格は、それぞれ「1級」と「2級」があります。この2つの違いは、1級を取得した場合には工事現場において「監理技術者」として仕事が行える点、2級を取得した場合には「主任技術者」として仕事が行えるという点にあります。
施工管理技士の1級と2級では、受験するために必要とされている実務経験の長さも異なります。1級の方が上位の資格となることから、もちろん必要とされる実務経験の年数も長くなります。
2級の第一次検定については、学歴・学科などを問わず17歳以上であれば誰でも受験可能。もしも、1級の受験に必要とされる実務経験年数を満たしている場合には、1級から受験することもできます。
施工管理技士の資格を取得したいと考えていても、受験条件や難易度などがよく分からずに悩んでいる方も多いようです。このページでは、それぞれの施工管理技士の試験について紹介しています。7種類ありますので、気になる資格の概要をチェックしてみてください。
第一次検定の受験資格については、最終学歴と保有資格により求められる実務経験年数が異なります。また、第二次検定の受験資格は「第一次検定の合格者」と定められていますが、2級合格者として受験した場合には、最終学歴や保有資格によって求められる実務経験年数が異なります。
第一次検定のみ受験する場合には、試験実施年度において満17歳となる方に受験資格が与えられますが、第二次検定を同時に受ける場合には最終学歴などによって受験資格が変わってきます。
<第一次検定(出題形式:四肢択一式・五肢択一式)>
<第二次検定(出題形式:問題1〜4は記述式、問題5〜6は五肢択一式)>
・前期
<第一次検定(出題形式:四肢択一式・四肢択二式)>
・後期
<第一次検定(出題形式:四肢択一式・四肢択二式)>
<第二次検定(出題形式:記述式・四肢択一式)>
平成29年〜令和4年の1級建築施工管理技士の合格率は、第一次検定は36.6〜51.1%、第二次検定は33.5〜52.4%で推移しています。比較的高い合格率といえるものの、受験資格を満たす人がかなり限られること、さらに受験する人が一定の知識を持っており実務経験豊富な人も多いことからこのような合格率となっていると考えられます。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/building)
平成29年〜令和4年の2級建築施工管理技士の合格率は、第一次検定は20.5〜50.7%、第二次検定は25.2〜53.1%となっています。第一次検定においては、開催年度が同じ場合前期試験の方が合格率が高い傾向があります。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/building)
受験の申し込みを行う場合には、書面による申し込みが必要です。必要書類を全て揃えた上で、指定の申込用封筒に入れて簡易書留郵便で郵送します。ただし再受験申込の対象者に限り、書面申込またはインターネット申込いずれかの申し込みが可能です。
<前期(一次のみ)>
<後期(一次・二次 / 一次のみ / 二次のみ)>
1級土木施工管理技士を受験するためには、実務経験が一定期間必要となります。実務経験の期間は学歴によって異なります。ただし、2級を取得している場合には、1級の第一次検定まではすぐに受験が可能となります。
2級土木施工管理技士において第一次検定だけを受験する場合には、試験が実施される年度で満17歳となる場合に受験が可能となります。ただし、第二次検定を受験する場合には学歴などによって受験資格の要件が変わってきますので、あらかじめ確認が必要なポイントであるといえるでしょう。
<第一次検定(出題形式:四肢択一)>
<第二次検定(出題形式:記述式)>
・前期
<第一次検定(出題形式:四肢択一)>
・後期
<第一次検定(出題形式:四肢択一)>
<第二次検定(出題形式:記述式)>
1級土木施工管理技士の場合、平成29年度から令和4年度の合格率は、第一次検定が54.6〜66.6%となっています。また、第二次検定の合格率は30.0〜45.3%です。第二次検定となると合格率が下がりますが、試験が開催される年度によって多少の差が出てくる傾向があります。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/civil)
2級土木施工管理技士の場合には、平成29年度から令和4年度の合格率は、一次検定が50.3〜71.6%と年度により幅があります。また、第二次検定においては34.3〜42.2%の合格率となっており、概ね30%台で推移しています。このように、第二次検定になると一気に合格率が低くなることから、難易度が高くなると考えられます。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/civil)
受験を希望する場合には、必要書類を揃えた上で簡易書留にて申し込みを行います。ただし、再受験者はインターネットでの申し込みが可能となっており、インターネット申し込みを行う場合には、申し込み用紙の購入は必要ありません。また、申し込みは受験者本人が行うことが必要となります。
<前期(一次のみ)>
<後期試験(一次・二次 / 一次のみ / 二次のみ)>
1級管工事施工管理技士試験を受験するためには、実務経験が求められます。例えば「大学・専門学校(高度専門士を称するもの)」の場合には、指定学科場合卒業後3年以上の実務経験、それ以外は卒業後4年6ヶ月以上といったように、学歴により必要な実務経験年数が異なります。
2級管工事施工管理技士の場合も、受験を希望する場合には実務経験を積む必要があります。こちらの場合には大学・専門学校(高度専門士を称する者)」であれば、指定学科の場合卒業後1年、またそれ以外の場合に卒業後1年6ヶ月以上の実務経験が求められます。学歴によって必要な実務経験年数が異なりますが、1級よりかなり早く受験資格が得られます。
<第一次検定(出題形式:四肢択一式・四肢択二式)>
<第二次検定(出題形式:記述式)>
・前期
<第一次検定(出題形式:四肢択一)>
・後期
<第一次検定(出題形式:四肢択一)>
<第二次検定(出題形式:記述式)>
1級管工事施工管理技士の平成29年〜令和4年にかけての第一次検定の合格率は、24.0〜52.1%となっており、試験を行った年度によってかなり開きがあることがわかります。また、第二次検定においては52.7〜73.3%の合格率でこちらも開催年度に差が出る傾向があるようです(第二次検定においては令和4年の合格率が確認できませんでした)。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/piping)
2級管工事施工管理技士の平成29年〜令和4年の合格率を見てみると、第一次検定においては50.4〜61.7%となっており、第二次検定では40.0〜46.2%で概ね40%台で推移しています(第二次検定は令和3年までのデータとなっています)。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/piping)
基本的には書面での申し込みとなりますので、必要書類を揃えた上で簡易書留郵便により郵送を行う必要があります。申し込みは受験者本人が行う必要がありますので注意しましょう。 また、再受験者の場合にはインターネットでの申し込みも可能です(こちらの場合には、試験申込にあたり申込用紙を購入する必要はありません)。
<前期試験:一次のみ>
<後期試験:一次・二次/一次のみ/二次のみ>
1級造園施工管理技士の試験を受けるためには、実務経験を積む必要があります。実務経験は学歴によって変わってきますが、例えば大学や専門学校(高度専門士と称する者)で指定学科を卒業している場合には3年以上の実務経験、また指定学科以外の場合は卒業後4年6ヶ月以上の実務経験が求められます。
第一次検定のみを受験希望の場合には、令和5年度中における年齢が17歳以上であれば受験資格が得られます。ただし第二次検定を受験する場合には、所定の実務経験が必要となります。1級と同様に学歴により必要な年数が異なりますので、自分の場合は何年の実務経験が必要なのかあらかじめ確認しておきましょう。
<第一次検定(出題形式:四肢択一式)>
<第二次検定(出題形式:記述式)>
<第一次検定(出題形式:四肢択一式)>
<第二次検定(出題形式:記述式)>
令和元年度から令和3年度までの1級造園施工管理技士の合格率ですが、第一次検定においては35.9〜39.6%、第二次検定においては39.6〜41%の合格率となっています。国家資格であることから決して難易度が低い試験ではありませんので、合格にためには実務経験として求められる年数相応の知識が必要となります。
参照元:資格の王道(https://www.shikakude.com/sikakupaje/zoenseko.html)
令和元年度から令和3年度の期間における2級造園施工管理技士試験の合格率については、第一次検定については49.8〜58.3%、第二次検定においては37.6〜43.0%となっています。1級と比較すると難易度が低く設定されているため第一次検定については独学でも合格を狙えるでしょう。ただし、第二次検定は記述式となることから、よりしっかりと試験対策を行うことが求められます。
参照元:資格の王道(https://www.shikakude.com/sikakupaje/zoenseko.html)
造園施工管理技士の試験の申し込みは書面での申し込みを行います。その場合には、簡易書留郵便を使用し、個人別で申し込みを行ってください。また、再受験者の場合にはインターネットでの申し込みも可能となっています。この場合には試験の申し込み用紙を購入する必要はありません。
<前期試験:一次のみ>
<後期試験:一次・二次/一次のみ/二次のみ>
1級電気工事施工管理技士試験を受けるためには、実務経験が必要です。どのくらいの実務経験が求められるのかは学歴によって異なるため、自分の場合は何年の実務経験が必要なのかを確認しておきましょう。例えば大学や専門学校(高度専門士を称する者)の指定学科を卒業している場合には、卒業後3年の実務経験が必要です。
受験資格を得るには実務経験が必要になります。例えば大学や専門学校(高度専門士を称する者)を卒業している場合で、かつ指定学科を卒業している場合には卒業後1年以上の実務経験年数が必要になるといったように、学歴によって受験資格が変わります。また、第一次検定のみ受験するという場合であれば、17歳以上であれば申し込みが可能です。
<第一次検定(出題形式:四肢択一式・五肢択一式>
<第二次検定(出題形式:記述式)>
・前期
<第一次検定(出題形式:四肢択一式・五肢択一式)>
・後期
<第一次検定(出題形式:四肢択一式・五肢択一式)>
<第二次検定(出題形式:四肢択一式)>
1級電気工事施工管理技士における平成29年以降の合格率としては、第一次検定が38.1〜56.1%となっており、また第二次検定においては58.8〜73.7%となっています。第二次検定においては高い時で70%を超える合格率となっていますが、試験までにかなりの知識や経験を積んでいると考えられるため、決して難易度が低いわけではないといえるでしょう。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/electric)
平成29年以降における2級電気工事施工管理技士の合格率は、第一次検定では50.0〜66.3%、第二次検定では43.2〜61.8%という結果になっています。年度により合格率に幅がありますが、いずれにしても合格するには受験資格にて求められている実務経験年数に伴う知識を身につけることが必要であるといえます。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/electric)
電気工事施工管理技士の場合、個人で必要書類を郵送して申し込みを行う方法のほか、学校単位で申請書を取りまとめて一括で郵送するといった方法があります。
<前期試験:一次のみ>
<後期試験:一次・二次 / 一次のみ / 二次のみ>
1級電気通信工事施工管理技士試験の受験資格についても学歴により変動がありますので、受験を検討している場合には実務経験がどれくらい必要なのかを確認しておきましょう。例えば大学・専門学校(高度専門士を称する者)の指定学科を卒業している場合には、卒後後3年以上の実務経験が必要です。
第一次検定のみの受験を希望する場合には、17歳以上であれば受験の申し込みが可能となります。また、第二次検定まで受験しようとする場合には、所定の実務経験を積むことにより受験することができます。1級と同様に、学歴によって必要な実務経験年数が異なります。
<第一次検定(出題形式:四肢択一)>
<第二次検定(出題形式:記述式)>
・前期試験
<第一次検定(出題形式:四肢択一)>
・後期試験
<第一次検定(出題形式:四肢択一)>
<第二次検定(出題形式:記述式)>
令和元年から令和4年の1級電気通信工事施工管理技士において、第一次検定の合格率は43.1〜58.6%で推移しており、第二次検定の合格率は30.1〜49.5%(二次検定は平成3年までのデータ)となっています。電気通信工事施工管理技士資格は新設されてまだ数年の国家資格となっているため、年ごとの合格率の幅が激しい傾向があります。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/denkitsushin)
令和元年から令和4年に実施された2級電気通信工事施工管理技士試験の合格率は、一次検定では50.5〜87.4%、第二次検定の合格率は30.1〜41.9%となっています(第二次検定については令和元年・令和2年・令和3年のデータ)。 2級の第一次検定においては、1級以上に合格率に幅がある状態となってはいるものの、やはり新設の資格であることが影響していると考えられます。
参照元:CIC日本建築情報センター(https://www.cic-ct.co.jp/course/denkitsushin)
基本的には必要書類を揃えた上で、簡易書留郵便による郵送にて受験の申し込みを行います。ただし、再受験者の場合に限りインターネットでの申し込みが可能となっており、その場合は申し込み用紙の購入は不要です。
<前期試験:一次のみ>
<後期試験:一次・二次 / 一次のみ / 二次のみ>
1級建設機械施工管理技士の試験を受験するためには、受験種別(第1種〜第6種)の建設機械に関する実務経験が必要と決められています。この実務経験年数については、学歴と卒業学科によって変わってきますので、自身の場合にはどれくらいの実務経験年数が必要なのかを確認しておきましょう。
第一次検定のみの受験を希望する場合には、受験する年の年度末に17歳以上になる方は誰でも受験が可能です。また、第二次検定を受けようとする場合には、実務経験の条件を満たす必要があります。1級と同様に学歴と卒業学科により必要な年数が決まっていますので、あらかじめ確認しておくことが大切です。
<第一次検定(出題形式:四者択一)>
<第二次検定(出題形式:記述解答方式)>
<第二次検定(実技・下記より2つの検定を選択して受験する)>
<第一次検定>
・共通の検定科目
・種別の検定科目
<第二次検定(記述解答方式)>
<第二次検定(実技・下記より2つの検定を選択して受験する)>
直近3年(令和2年度〜令和4年度)の1級建築機械施工技士の合格率は、第一次検定が20.3〜26.4%、第二次検定については52.7〜80.2%となっています。
参照元:資格の王道(https://www.shikakude.com/sikakupaje/kenchikukikaiko.html)
1級と同様に、令和2年度〜令和4年度の2級建築機械施工管理技士の合格率は、第一次検定が42.8〜55.5%、第二次検定が68.2〜82.5%となっています。
参照元:資格の王道(https://www.shikakude.com/sikakupaje/kenchikukikaiko.html)
必要書類を準備した上で簡易書留により郵送を行い、申し込みを行います。郵送には専用の封筒を使用する点にも注意が必要です。
施工管理技士をはじめ、建設業界で有利に働く資格試験に合格するには、「スクール」「通信教育」「独学」という3つの方法があります。こちらでは各学習法のメリット・デメリットを紹介します。
建設業界の資格を取得するには、資格を取るための専門スクールに通う方法があります。
通学するメリットは、資格合格に直結する講義内容を受けられること。充実した講師陣による講義を受けられることに加えて、疑問点や質問は講義中に解消できます。
反対にデメリットととしては、スクール受講料がそれなりに高いこと、決められた曜日・時間に通学する必要があることが挙げられます。近隣にスクールが少ない地域の場合、通学時間や交通費も負担となりやすいでしょう。
2つめは、通信講座で学習する方法です。
通信講座はスクールへ通学する必要がないため、自分のペースで、場所を選ばず学習できるメリットがあります。また対象資格試験にターゲットを絞っているため、合格に直結する内容をそのまま学べます。授業は主に教材(テキストや動画など)による自主形式となりますが、不明点や相談などは電話やメールで問い合わせることも可能です。
ただし、スクールと同様に受講料が必要となります。ネット通信環境が整っていないと、受講が困難なケースも。また自分のペースで進めていくために、スケジュールや勉強に関する自己管理を怠ると、いつまで経っても資格が取れないといったデメリットもあります。
3つめの学習方法は独学です。対象試験のテキストや過去問題を購入し、必要な知識を頭に入れていきます。
独学は自分のペースで場所を選ばず学習でき、テキスト・問題集などの書籍を購入するだけで可能なため、経済的負担は少なく済むでしょう。
しかし、学習スケジュールの管理を徹底して行う必要があります。また不明点は自身で解消しないといけないため、難易度が高い方法と言えるでしょう。
施工管理技士の資格を取得するためには、まずは「選択式(4択)の試験問題集に取り組む」という点がポイントです。選択式の問題は、出題傾向の対策を行うことによって問題の本質を100%理解していなくても正解に辿り着きやすいためです。まずは、選択式問題を繰り返し解いて傾向を把握するように勉強することをおすすめします。
また、問題集を中心に勉強していくこともポイントのひとつです。特に、1冊の問題集を何回も繰り返して解くことが重要。さまざまな問題集に取り組むのではなく、同じ問題集を繰り返し解くことによって、問題と解答が記憶に定着していくのです。
働く職種に関わる資格を取得すれば、資格手当が支給されて給与が増加したり、奨励金を受けとれる会社が増えています。従業員が資格を取得することで、任せられる業務の幅が広がり会社にとって有利に働くからです。
会社によっては、教材などの資格取得に関わる費用や試験費用などを負担してくれるサポートもあります。会社ごとに支援内容は異なるため、事前に就業規則や資格制度をチェックしておきましょう。
資格の取得は、その方面の知識とスキルを持っていると客観的に証明してくれるものです。社内での評価だけでなく、クライアントや工事現場の職人に対しても示すことができ、信頼を得るひとつの手段でもあります。
また、これまで紹介してきたような国家資格を取得していれば、率先力がある人材として転職にも有利に働きます。
難易度の高い資格を取得するほど会社からの評価や待遇が向上します。特に国家試験である施工管理技士関連の1級などは、最終学歴後の実務経験と専門知識の両面が必要になるため難易度が高く、評価を上げるのに効果的。
資格の取得が出世条件になっている企業もあり、資格取得によって責任ある新たな仕事を任せられ、実力を認められれば給与アップも期待できます。
客観的スキルの証明になる建築関連の資格は、転職活動で強力な武器になります。慢性的な人手不足である建築業界は、責任ある役職も人が足りず常に人材を求めています。国家試験1級の受験資格などは、実務経験が必要とされるため、知識とスキルの両面が揃っていることが合格基準です。
企業側は即戦力ある人材を常に求めているため、資格を取得している人を高く評価します。より条件のよい企業へ転職するために資格は大いに役立つでしょう。
資格試験には、今まで実務経験したことのない分野や内容の項目を含む場合もあります。しかし、受験勉強をすることで、経験したことのない範囲の知識も身につけることができたり、経験済みの事柄をさらに深く理解することが可能です。
資格取得にはさまざまなメリットがありますが、未経験から資格取得を目指すのはもちろん簡単なことではありません。何度も繰り返し勉強することが求められますが、場合によっては働きながら資格取得を目指すケースもあるでしょう。
働きながら資格取得を目指す場合、企業のなかには従業員の資格取得を支援する制度を設けているところもあります。仕事と勉強の両立はそう簡単なことではありませんので、こういった支援制度を用意している企業を選ぶことも、未経験からの現場監督を目指すうえでは大切です。
当サイト取材協力会社についてまとめているこちらのページでは、未経験から現場監督を目指せる同社の特徴について紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
現場監督として働きながら資格取得を目指すなら、平日の昼間は当然勉強する時間はあまり取れません。夜間や早朝、休日などの時間を割いて勉強に充てる必要があります。
それゆえ、仕事が忙しい時などは、心が折れて諦めてしまうということが起きがちです。逆に勉強に熱中するあまり本来の仕事に影響が出てしまうという事態にも要注意です。
取得を目指す資格の種類にもよりますが、なかには猛勉強を必要とするような、狭き門のものもあります。それこそ生半可な気持ちでは合格など夢のまた夢で、1,000時間の勉強を重ねて初めて合格の希望が持てるといった場合も。
日々の仕事を終えたあとの夜間、あるいは始業前の早朝に時間を設け、コツコツと勉強を積み重ねるといった覚悟と信念が求められます。
建築関連の資格のなかには、まずAという資格を取得することで、Bという資格の受験資格が得られるといったケースもあります。この場合、最初から直接Bという資格を取得することはできず、Aの資格を取得するための勉強から始めなければなりません。
取得したい資格がある場合には、まず受験資格がどうなっているかをしっかり調べ、前段階の資格取得が必要か否かをチェックする必要があります。
ここでは、現場監督として仕事をする上でおすすめの資格について紹介していきます。
設計分野で役立つ資格としては、建築士があります。1級また2級建築士を取得しておくのがおすすめですが、この2つは設計できる建物の規模に違いがあります。ちなみに1級の場合は設計できる建物の大きさに制限がないことに対し、2級の場合には戸建の設計などを行います。
現場監督の仕事に設計士資格は必須ではないものの、待遇面などでメリットを感じられる可能性があります。ただし簡単に取得できる資格ではないため、しっかりと集中して勉強できる工夫が必要になってきます。
さまざまな電気設備の保管監督業務を行うために必要な資格であり、第一種から第三種まであります。その中でおすすめは第二種または第三種電気主任技術者の資格です(第一種は電力会社で仕事をするときに必要な資格となります)。
合格するためには発電や配電などに関する知識が必要であることに加えて、数学などの知識も必要。かなりの時間を勉強に充てることが必要となります。
施設に設置してある消火設備の点検や整備、工事を行うための資格が消防設備士です。消防設備とは、消化器やスプリンクラーなどを指します。資格の種類は点検や整備、工事の全てを行える「甲」と、工事以外を行える「乙」の2種類があります。消防設備士の資格を取得すると、建設現場でも消防設備の工事などを行うことができるようになります。
消防設備の点検を行う場合に必要な資格となります。3日間の講習を受けると取得できる資格であるものの、講習を受講するためには管工事施工管理技士などの資格を持っていることが条件となります。受講条件を満たしていない場合には講習を受講できない点に注意しましょう。
マンションにおける修繕工事やマンション組合の運営サポートを行うなど、マンションの維持管理を行うための資格です。試験問題としては、建築基準法や都市計画法、消防法、水道法など幅広い分野が対象となってきます。そのため、この資格を持っていると幅広い知識があることを証明できます。
「宅建」とも呼ばれるこちらの資格は、不動産売買や賃貸契約を行う場合に重要事項説明を行う場合に必要な資格です。試験では宅建業法施行規則や民法に関する問題が出題されますので、建物に関係する法律についての知識があるという点を証明できます。
不動産売買や相続などの手続きを行う場合に、不動産の正確な価格について調査を行い、評価を行うための資格となっています。その他にも、不動産を有効活用するためのアドバイスも行うため、不動産に関係する知識を持っていることを証明できます。
コンクリートについて点検や診断を行い評価できる資格です。コンクリートは建築現場で欠かせないものであるため、現場監督として仕事を行う上で役立てられるでしょう。試験を受ける前に、2日間の試験前講習を受講する必要があります。
ご覧いただきました通り、現場監督が仕事上で活用できる資格は多種多彩です。その一方で、資格ごとに難易度や取得後のメリットは異なります。以下に、各資格を難易度別に分類してみました。ご自身の目標や現状を鑑みながら、どの資格しぃとくを目指すべきか、参考にしてみてください。
建築業界において難易度の高い資格と言えば、建築士、施工管理士、技術士といったところが代表格です。また、それぞれに「一級」や「二級」といった等級があり、当然上位の方が難易度はより高くなります。
取得にあたっては多大な努力を要しますが、取得すれば地位や収入アップにつながりやすいという明確なメリットがあります。
建築業界での実務経験がない、少ないという場合でも、比較的取得しやすい資格としては、建築CAD検定、キッチンスペシャリスト、建設業経理士検定などがあります。
ただし、一定の知識は必要。建築CAD検定なら建築設計に関する内容、キッチンスペシャリストであれば建築設計プラス住宅設備や機器に関する知識や情報、建設業経理士検定だと簿記や会計に関する知識といった具合です。
建築業界で一定レベルの実務を経験した方であれば、特定の講習を受講することで取得できるというタイプの資格もあります。労働安全衛生法で規定された国家資格である作業主任者が、その筆頭格。
特定の工事現場で安全を担保する役割を担う存在であり、各種の技能講習修了者のなかから選任されるという仕組みとなっています。規定された講習を受講後、一時間程度の修了試験に合格すれば、作業主任者に任命される資格が与えられます。
そもそも資格というものは、取得すること自体が目的ではなく、取得した資格を有効に活用し、ご自身のキャリアアップに役立てるということが本筋です。それゆえ、闇雲に資格を取りまくればいいという考えはNG。
重要なのは、ご自身が今携わっている業務に役立つか、将来的な展望にマッチしているかといった観点で、どの資格を取得するかを考えることです。
前述しました通り、建築関連の資格のなかには、比較的難易度が低いものもあります。しかしながら、何もせずのほほんとしていても取得できるほど甘いものではありません。
狙う資格の難易度にもよりますが、例えば資格試験が実施される日程から逆算し、1日1~2時間程度の勉強を2~3ヶ月程度行うといった計画をしっかりと立てて実践するといった対策が不可欠です。
ここでは、おすすめの資格取得の組み合わせを種類別に説明していきます。
土木工事の現場監督は、土木施工管理技士や建設部門の技術士資格を取得するのがおすすめ。ゼネコンに転職しやすいだけではなく、建設コンサルタントや公務員などキャリアの選択肢も広がります。今後のキャリアのためにも、資格取得を検討するとよいでしょう。
電気工事施工管理技士や電気工事士の資格を取得するとよいでしょう。電気工事施工管理技士が電気工事士を取得しておくと、電気工事の技術面がわかるだけではなく、電気工事士とスムーズなコミュニケーションがとりやすくなります。また消防設備の知識が必要な場合であれば、消防設備士の資格も取得しておくのがおすすめです。
管工事の現場監督におすすめの資格として、管工事施工管理技士や配管技能士の資格が挙げられます。電気工事と同じく、管工事施工管理技士が配管技能士も取得することにより、技術面に関して配管工の職人と仕事上必要なコミュニケーションが取りやすくなります。信頼が得られやすく、仕事もスムーズに進められるでしょう。
造園工事の現場監督は、造園施工管理技士や造園技能士などの資格を取得しておくとよいでしょう。こちらも同様に、造園施工管理技士が造園技能士を取得しておくと、庭師やそのほか現場に関わる職人と技術面の話をしやすくなるメリットがあります。スムーズなコミュニケーションが取りやすくなるため、仕事を進めやすくなるはずです。
例えば特定の資格を取得し、日比の業務に有効活用することができれば、ご自身のキャリアを高めるチャンスをより広げるということにもつながります。どのようなケースが考えられるか、一例をご紹介しましょう。
まず2級施工管理技士の資格を取得することで、外注総額が4,000万円未満の現場の主任技術者を務めることができるようになります。そうした資格を活かしながらの現場経験を重ねていき、その上で1級施工管理技士に合格できれば、外注総額が4,000万円以上または建築一式6,000万円以上の大規模プロジェクトに、主任技術者・監理技術者として参加できるようになります。
上記のような資格を活かして、様々な現場での経験を積み重ねていけば、将来的には本部で施工管理部門全体のマネジメントに携わるといった道のりも見えてきます。
例えば複数の現場を統括する立場として、現場を巡回して安全管理や技術指導、調整業務を行ったり、チームメンバーの育成や、工事状況の進捗管理といった、包括的な管理業務を担う立場となります。
取材協力会社
株式会社テクノプロ・コンストラクション
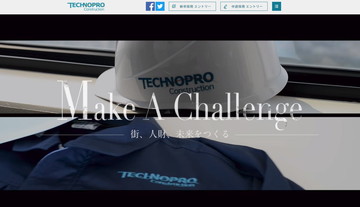
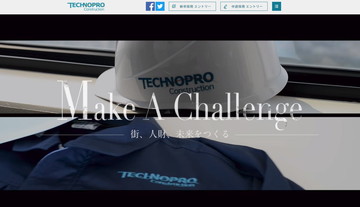
スーパーゼネコンをはじめとした、建設業界大手を中心に、質の高い技術を提供できる人材を派遣している、テクノプロ・コンストラクション。
2000名近い技術者のうち、未経験者からベテランまで幅広いメンバーが在籍しています。誰もが知っている有名なビルや施設など、数多くの優秀な建設技術者たちが活躍中です。 施工管理や建築について学べる1ヵ月の研修や、先輩担当者のフォロー・サポート体制が充実しているため、未経験で不安なかたもすぐに現場監督になれる環境が整っています。